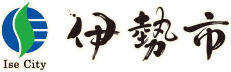聞く(おうち企画展)
蓄音機(ちくおんき)

蓄音機は、明治10年(1877)にアメリカのエジソンが発明しました。写真は、円盤式の蓄音機です。レコードの表面には、回転に合わせた細かな溝が彫られており、その溝に針があたることで、振動し、音ができる仕組みです。明治40年(1907)には、国産品が作られ始めましたが、本格的に普及していったのは、戦後の1950年代からでした。とても高価なものであったため、庶民の憧れの品でした。
ラジオ

ラジオの放送が本格的に始まったのは、大正14年(1925)のことです。当時は、世の中の出来事を知るすべとしては、新聞くらいしかなく、ラジオは画期的なものでした。放送当時のラジオは、聞くのにお金がかかりましたが、それでも多くの人々は、情報を求めてラジオを聞いていました。
磁石式電話機

電話が一般的に使われるようになったのは、明治23年(1890)に東京と横浜間で電話線が引かれてからです。この当時の電話は、直接電話したい人に電話するのではなく、交換手という人に電話をして、つないでもらうものでした。磁石発信機から交換手に信号を送るので「磁石式」と呼ばれています。
ダイヤル式電話機

戦後の1950年代からは、これまでの磁石式に替わり、「黒電話」と呼ばれるダイヤル式の電話機が登場しました。電話のかけ方は、まず電話したい番号の穴に指を入れます。そのまま、ダイヤル0番の側にあるストッパーまで回します。ダイヤルはバネの力で、元の位置に自動で戻るため、繰り返し番号を回すことで、相手に発信することができます。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
文化政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-22-7885
ファクス:0596-21-0424
文化政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。