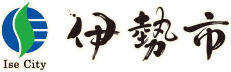高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担限度額の合算
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間(毎年8月から翌年7月分)の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が申請により高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:毎年8月から翌年7月)
70歳未満の人(平成27年8月から)
| 所得区分 |
所得要件 (国保加入者全員の所得合計額) |
国保+介護保険の 自己負担限度額 (70歳未満を含む) |
|---|---|---|
| 上位所得者(ア) | 旧ただし書き所得901万円超 |
212万円 |
| 上位所得者(イ) | 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
| 一般(ウ) | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
| 一般(エ) | 旧ただし書き所得210万円以下 |
60万円 |
| 低所得者(オ) | 住民税非課税 |
34万円 |
旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。基礎控除額は住民税の基礎控除額と同じです。
対象となる所得は、前年中(1月から7月の間は前々年中)の所得です。
70歳から74歳の方
| 所得区分 | 所得要件 |
国保+介護保険の 自己負担限度額 (世帯内の70歳から74歳) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 (高齢受給者証の負担割合が3割の人) |
212万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上690万円未満 (高齢受給者証の負担割合が3割の人) |
141万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ |
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
| 一般 | 課税所得145万円未満(※1) (現役並み所得者および低所得Ⅰ・Ⅱ以外の人) |
56万円 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 (世帯主および同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税である世帯の人) |
31万円 |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 〔世帯主および同一世帯の国保加入者全員の所得が0円(年金の所得は、控除額を80万6,700円として計算)の世帯の人〕 |
19万円 |
対象となる所得は、前年中(1月から7月の間は前々年中)の所得です。
(※1)同一世帯の70歳から74歳の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
(※2)低所得Ⅰの所得区分に相当する世帯で、複数の人が介護サービスを利用する場合には、医療費合算算定基準額は31万円になります。
70歳から74歳の方と70歳未満の方が混在する場合
まずは70歳から74歳の方にかかる自己負担額の合算額に、70歳から74歳の区分の自己負担限度額を適用し、なお残る負担額と、70歳未満の方にかかる自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額を適用します。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。